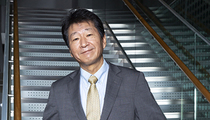社会課題をデジタルの力解決することがDXのエッセンスと語る、日本オラクルのケネス・ヨハンセン 執行役CEO
社会課題をデジタルの力解決することがDXのエッセンスと語る、日本オラクルのケネス・ヨハンセン 執行役CEO
「デジタルニッポン再生論──ITトップが説く復活へのラストチャンス」#2
ビジネスや社会のデジタル化、いわゆるDX(Digital transformation=デジタルトランスフォーメーション)の日本の状況は、世界から見てどんな位置づけにあるのか。IT業界のトップにDXとは何かを訊いて歩く連載「デジタルニッポン再生論──ITトップが説く復活へのラストチャンス」。第2回の今回は、日本オラクルのケネス・ヨハンセン執行役CEOだ。この9月、着任したばかりのヨハンセンCEOの目に、日本のDXはどのように映ったのだろう。
世界のデータベースのトップを走るOracle(オラクル)。マイクロソフト、IBMと並び称されるソフトウェアの世界企業だ。設立は1977年。79年にリリースした最初のバージョンのOracle Databaseは、世界初の商用リレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)といわれている。
日本法人の日本オラクルの設立は85年。以来30年あまりにわたって、日本でもデータベースのキープレイヤーとして重要なポジションを占めてきた。10年以降、データベースにとどまらず、サーバーやストレージ、関連サービスも提供している。
着任して数週間。現時点の感想としてヨハンセンCEOは、「すでにあちこちでDXの議論を交わしてきたが、日本は欧州とほぼ同じレベル。進展に関して、日本企業が謙遜したり卑下したりする必要はない」と話す。
8月までデンマークやドイツのカントリー・リーダーを務めるなど、欧州での経験が豊富な彼の目には、日本の現状は欧州と同じような段階にあると映ったようだ。「中小企業から大企業まで、欧州全域でもデジタル化は大きな課題になっている」という。
日本と欧州で共通する問題は高齢化だ。少ない若年者でサービスの量と質を維持していくためには、効率化が不可欠。そういった視点からDXが語られることが多いという。「もちろん他国から労働力を迎え入れて解決するというアプローチもある。しかし、デジタル技術を使って解決する方法もある」とヨハンセンCEOは話す。
つまり、「高齢化のような社会課題をデジタルの力を使い、プロセスを効率化することで解決する。そのエッセンスがDX。オラクルもその一翼を担っている」わけだ。最も分かりやすい効果は「自動化」だ。「手作業で行っていることを、自動化することでソースを開放し、本質的な価値の創造に振り向けることができるようになる」という考え方だ。
日本の社会や企業がDXを必要とする要因はまだある。それは、すでにDXでビジネスを拡大している競合が世界に存在するからだ。「既存企業が、成長著しい新興企業との競争にさらされるようになってきた」とヨハンセンCEOは指摘する。有線電話回線の普及を飛び越してスマートフォンの普及が一気に進みつつあるアフリカのように、新興企業は新しい技術を安価ですぐに取り入れることができるという、大きな変化が生まれている。
従来であれば新興で中小規模の企業であっても、ネットワークの構築、サーバー設置、ストレージを設け、アプリケーションを構築することを求められ、独自のリソースが必要とされてきた。しかし、現在は、クラウド型のサービスを一定の利用料を支払って使う「サブスクリプションモデル」で、安価に構築することができる。
さらに、「オラクルでは、ブロックチェーンやAIを活用したサービスもサブスクリプションモデルで提供している。スペシャリストでなくても、数学のアルゴリズムの専門知識がなくても、誰もがシリコンバレーのイノベーションを利用できる」ことが、大きな力を生むわけだ。
新興企業は、こうした恩恵を積極的に活用しながら新たなビジネスを創造している。一方、既存企業は、自らが抱える現用のシステムが足かせになり、最新のテクノロジーの恩恵を受けられないままでいる状態が生じつつある。例えば、クラウドサービスを使いこなせる人材の不足もその要因だ。
「過去20~25年の間、効率化を進めるために既存企業はさまざまなITリソースをアウトソーシングし、コスト削減を進めてきた。今度は、自身がテクノロジー人材をもち、競争しなければならない状況に変化してきている」(ヨハンセンCEO)。
ここで必要とされる人材とは、「イノベーションが手軽に利用できる環境が進む中、複雑なアプリケーションをビジネス側主導で構築できるようになってくる。そこでは、ビジネスと技術をバランスよく理解できる人材だ」とヨハンセンCEOは説く。
欧州や日本に比べ、アメリカや中国がDXの取り組みがはやいのはなぜか。「アメリカの企業には、リスクを取ることを厭わないという文化がある。アプローチもトップダウン。ひとたび決断したら突き進む。加えて、エリアにも寄るが投資資金も潤沢だ。大学と産業のつながりがしっかりしているという理由もある」。
確かに、中国も似ている。例えば、深センでは、まさに同じような潤沢な資金を背景に進んでリスクを取る文化が、新しいテクノロジーを日々生み出している。
では、日本や欧州の企業は「まだ間に合う」のか。「特に日本の中堅企業にとって、これから成長するためには、その原動力を海外に求める必要があると思う。その際、戦うのは海外ですでにデジタル技術を活用してビジネスを拡大しようとする企業だ。残念ながら、デジタル化という列車はすでに出発してしまっている。しかし今なら、飛び乗ればまだ間に合う」。
しかし、飛び乗って何が変わるのか。ヨハンセンCEOはオラクルとして、企業への啓蒙活動を通じてDX推進を支援しているという。「この2~3年で、中小企業を対象とした専任部隊が活躍している。社内で400~500人の大所帯で、お客様と直接やりとりしながら、イノベーションで何が可能かを直接お伝えしている」と話す。
経営者がDX推進を決断したとき、何から始めればいいのか……。「まずは、オラクルに電話をしてほしい」と、ヨハンセンCEOは笑いながら話す。
加えて「とにかく事例が豊富だ。すでに成功している類似の企業や組織が必ずあるはず。例えば、日本のホテルチェーンであっても欧州のチェーンと同じ悩みを抱えているかもしれない。税金の処理にしても、東京もロンドンも同様の課題に直面しているかもしれない。グローバル企業のオラクルだからこそ、グローバルでさまざまな課題や機会の情報も得ることができる。オラクルのERPクラウドの顧客は2万社。1社のアイデアを広く共有することもできる」と自信を見せる。
オラクルが日本の中小企業のDX推進を支援する手法としては、「デジタル手法を活用した関係強化を図っていきたい。例えば、東京の企業のニーズに合うスペシャリストはコペンハーゲンにいるかもしれない。すぐにそれらをつなげることもできる利点を、デジタルによって最大限に活用したい」といい、ここでも世界企業である利点を最大限に活かす方針だ。
最後にヨハンセンCEOはDXを、「お客様が持っているデータの潜在的な可能性を見出し活用することで、無限の可能性をとらえていくことだ」と位置づけた。さらに、「データサイエンスを筆頭として、社会全体が若い世代への教育投資をする必要がある。ドイツや日本では、エンジニアは製造業に入り車を作るという道を歩むことが主流だった。しかし今、車はソフトウェアの塊。求められる技術は大きく変貌している。目まぐるしく変わる環境で、若い世代が競争力を発揮できることが重要だ」と結んだ。(BCN・道越一郎)