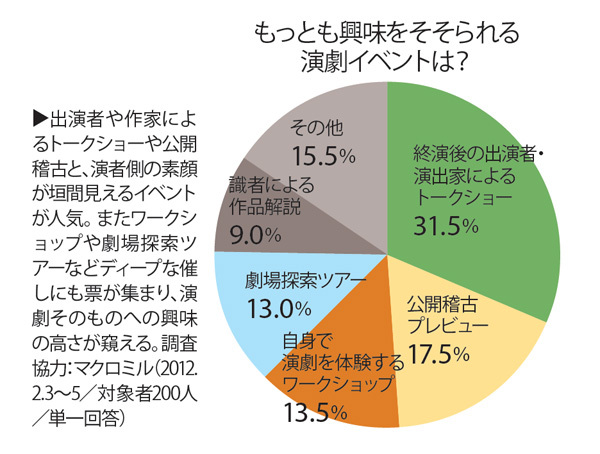こうした状況を支える背景には、まず、観客が潜在的に多角的な好奇心を持っていた、という素地がある。小劇場から始まったこの流れは、いまや商業演劇でも採り入れられ、バックステージツアーなどの形で展開されているが、ほとんどの企画はチケット代のみで参加できることもあり、反響は非常に大きい。
と同時に、演出家や劇作家が自作について積極的に語るようになってきたことがある。20代の作・演出家は、「ここでいくら喋ってもアイデアは枯れない」という自信なのか、「同じ場所にいる人たちで多くのものをシェアしたい」という素直さなのか、トークイベントを積極的に捉えている。そして、かつては「伝えたいことは作品にすべてある」と言っていたベテラン世代の中にも、作品づくりについて観客の前で話すことへの抵抗が薄れてきた人は多い。成熟が若き日のこだわりを溶解したケースもあるだろうし、いつの間にか作品の規模が大きくなり、それを反映してチケット代が高くなり、結果的に若い観客との間に距離ができてしまい、それを埋める手立てを模索しているケースもあるようだ。
もちろん、世代を問わず表現者にとって「伝えたいことはあくまでも作品の中」なのだが、それを前提として、まだ見ぬ観客にリーチを伸ばすため、できることは何でも試したいという意識を感じる。観客減少の危機感という見方もできるが、開かれた表現へと向かう無意識が、演劇全体に浸透し始めた予兆かもしれない。
関連記事