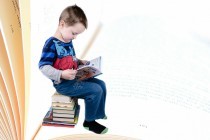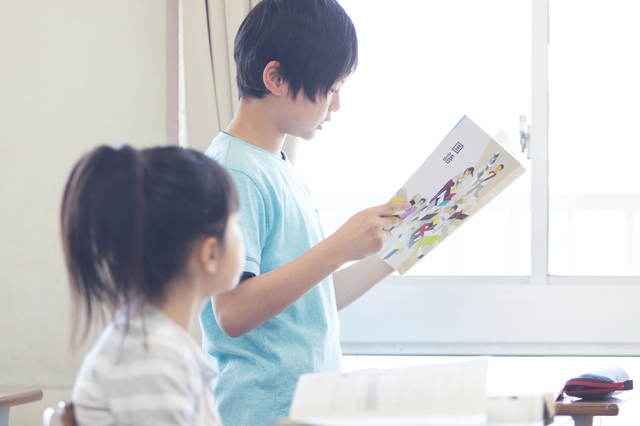
算数(数学)や英語は出来るのに、なぜか国語は出来ない、そんな子供が増えています。
国語は日本語だからそんなに勉強しなくても出来るだろう、と他教科に比べ軽視されがちですが、中学受験や高校受験で苦戦する教科が「国語」であることは少なくありません。
今や算数(数学)や英語は出来て当たり前!国語を制する者は受験を制すると言われるほど、「国語」に注目が集まっています。
しかし国語ばかりに力を入れるわけにはいかず、親としては「国語力は自然に養ってもらいたい」と思うものです。
そこで今回は出口 汪著『子どもの頭がグンと良くなる!国語の力』を参考に、幼少期からの会話で自然に国語力を身に着ける方法についてお伝えします。
国語が出来る、出来ないは「センス」ではない?

センスがある、ないという話は、生まれ持ったもののような気がして「仕方ないか」と諦めてしまいがちですが、国語が出来る、出来ないはセンスではありません。
物語を「読む」ことと、「読み解く」ことは全く別物。読み解くとは作者の意図を理解した上で作者の立てた筋道を辿るということです。
ですから、国語の問題を解く時は「自分はこう感じる」といった主観的考えは必要なく、あくまでも作者の意図することを解くことに意識を向けるということ。正しく学べば国語はできるようになると言います。
親の意識次第で、子供の国語力は養われる?
幼い頃の親子の会話は国語力を養う上でとても重要だと『子どもの頭がグンと良くなる!国語の力』著者である出口さんは言いますが、どこをどのように意識したら良いのでしょうか。早速見て行きましょう。
「主語」と「述語」を意識する

親子の日常的な会話は省略型が多いのが現実です。例えば「〇〇くんと喧嘩した」という会話は「いつ」「どこで」が抜けており、主語がないため状況が伝わってきません。
親子だから詳しく説明しなくても伝わるだろうという安易な考えがそのような会話を生んでしまうのでしょうが、どんな会話にも主語と述語は必要です。親子の会話もちゃんと意識すれば、国語力は自然と養われます。