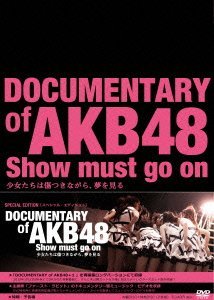蜷川幸雄に見せたかった。
『毒島ゆり子のせきらら日記』第8話のことである。
小津(新井浩文)との対峙が、真田弁護士(バカリズム)取り仕切りの下、おこなわれるこの回は、ほぼ3人だけの密室劇が展開、まるで舞台を見ているような迫真の息吹きが持続した。
はたして、蜷川が見たとして、どう感じるかはわからないが、少なくとも、この回の前田敦子は、2014年の初舞台『太陽2068』(演出:蜷川幸雄)では出来なかったことが出来るようになっていた。
前田の演じ手としての弱点は呼吸である。
前田敦子は、独特の台詞回しがある。それは得難い個性である。
ドキュメンタリー映画『DOCUMENTARY of AKB48 Show must go on 少女たちは傷つきながら、夢を見る』(2011)には、コンサートの舞台裏で壮絶な過呼吸に陥る前田の姿が収録されている。
もちろん、過呼吸と、演技の呼吸とは、まったくの別物ではあるが、これまで前田敦子の演技を見つめてきて、「息をどう回すか」ということについてあまりに無防備すぎて、危なっかしさを感じてきたのも事実である。
前田は自身の過呼吸映像を眺めながら、「人間、必死になりすぎると、こうなるんだなあ」と他人事のような感想を、テレビ番組で漏らしていたが、前田は演技に必死になりすぎて、芝居の呼吸がストリーム(流れ)を形成していかない面が少なからずあった。
が、前3章までに記してきたように、この弱点を補ってあまりあるほどの個性が、そして映画的な全身表現が、彼女にはあるから、むしろ、このアンバランスさは、唯一無二の情感醸成にもつながっていたのである。
『太陽2068』での役は、演劇としては決して多い台詞量ではなかったが、アップ&ダウンのあるヒロインだったため、後半は(熱量ではなく、演技の質として)文字通り「息切れ」が生じていた。失速は、初舞台だから、というより、演技呼吸そのものの弱点の露呈が要因だったと考えられる。
ところが、2015年の舞台『青い瞳』(演出:岩松了)では、登場人物のなかでだれよりも危険な場所の淵に立ちながら、だれよりも覚醒している状態(つまり、狂気を超えた狂気)のヒロインを体現、大いなる成長を感じさせた。だが、呼吸法の抜本的な改善ではなかったように思う。
前田敦子は、独特の台詞回しがある。それは得難い個性である。だから、もし、芝居の息をうまく回せるようになることで、その個性が失われるようなことがあってはいけないと個人的には考える。合理性に富んだ呼吸法よりも、はるかに尊い台詞回しが、演じ手としての彼女の魅力だからだ。
第8話は、技術の向上が、彼女にしかない個性に追いつきつつあることを感じた。