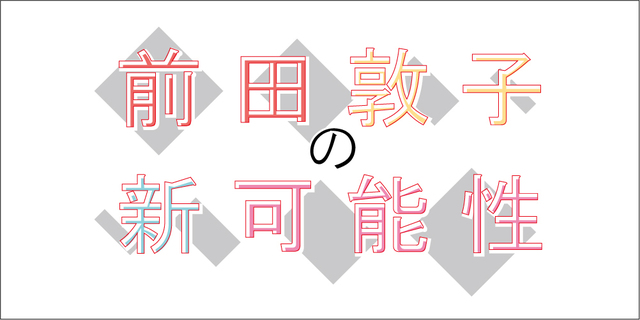
前田には代表作がなかった。
最終回の前の回がいちばん面白い。優れた連続ドラマにおいて、よく言われることである。
第8話で、物語上のピークを迎えた『毒島ゆり子のせきらら日記』。第9話は激しい展開があったわけではなかった。
祭りのあとのような、ダウナーな余韻にひたるエピソードであった。
だが、この回は、わたしたちにある結論をもたらした。
もう「元AKB48の」という肩書きは必要ない。
これからは「『毒島ゆり子のせきらら日記』の前田敦子」と呼ぶべきである。
「山下敦弘、黒沢清ら、日本を代表する映画監督たちに認められている女優」というまわりくどい前説もいらない。
女優を名乗る以上、代表作は欠かせない。
前田には代表作がなかった。
たしかに『もらとりあむタマ子』はそれに近い高水準の映画だった。だが、あくまでも彼女の魅力が存分に活かされた作品であり、女優力が全面的に発揮されていたかと言えば、そうとも言いきれなかった。
この論考でたびたび取り上げている『マジすか学園』(第1シーズン)にしてもそうだ。前田のポテンシャルを証明する連続ドラマではあったが、ナイスキャスティング(それはAKB48のなかで彼女にどのようなポジションを与えればいいかということに直結していた)であることが何よりの成功だった。
つまり、『もらとりあむタマ子』における達成は、山下敦弘の演出によるところが大きいし、『マジすか学園』における存在感は、秋元康の采配によるところが大きかった。
『毒島ゆり子』は、脚本も演出も素晴らしいが、プロデューサーの着眼点が何よりも素晴らしい。
前田に、変わり者やアウトサイダーを演じさせるのではなく、共感度の高い主人公を演じさせる。この野心と挑戦は、それが無謀だったからこそ、鮮やかな成果をいま残しつつある。
前田敦子にあわせて唯一無二のキャラクターを造形するのではなく、だれもが経験するかもしれない高揚と墜落を抱える「ありふれた」女性像を器として、そこに前田を放り込む。
政治記者経験もあるという、この女性プロデューサーの英断が、功を奏した。
『毒島ゆり子』こそが、前田敦子の真の代表作である。
そして、それは、ハマリ役などという陳腐な言葉で表現されるべきものではない。
前田が、己の持っている女優力のすべてを結集しなければ太刀打ちのできない、普遍的な器だったからこそ、本作は輝いている。
だれかに「引き出される」のではなく、自ら「注ぎ込む」。








