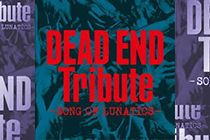MORRIE (撮影 川崎栄治)
MORRIE (撮影 川崎栄治)
DEAD END初期に比べたら、同一人物とは思えないくらい変わっていると思う
――旅がお好きなのは昔からですか?
MORRIE:いや、まったく興味はなかったんです。部屋にじっとして本を読んだり思索する方が好きだった。ところが、去年の3月ですよ。青木くんが亡くなる少し前に、一人旅をしたんです。
ツアーでは色々な場所に行ったことはありますが、自分で旅をしたいということはまったくなかった。なんだか、ふと、「魔が差した?」というのかな(笑)、妙な風が吹いたんでしょうね。そこから時間見つけて、旅に出ることが増えましたね。
――それは日本国内ですか?
MORRIE:そうですね。日本が面白い。複雑な地形から来る色んな形態の自然があるじゃないですか。自然の中に行きたいんですよね。「自然」とは何かという問いは置いといて。日本の自然ですね。
アメリカの自然はグランドキャニオンとか? 行ったことないですね。行ったらすごいんでしょうけどね。もちろん、世界にも、エジプト行きたいとか北極行きたいとかはあるけれど、日本は調べれば調べるほど興味深い場所が出てくる。
できるだけ自然の中に身を置きたいんですよね。子供の頃は自然の真っ只中にいて、それが嫌で飛び出してきたわけだけど(笑)。今はこれから春だし、誰もいない山の中へ行って、沢のせせらぎや梢の音、鳥の声を聴きながら自然の何かと同調するというか。
 MORRIE (撮影 川崎栄治)
MORRIE (撮影 川崎栄治)
――そんな旅で得たものも、作品に落とし込まれているのでしょうか。
MORRIE:旅自体が目的ではないからね。まあ、間接的には関係していると思いますよ。
――『光る曠野』というアルバム全体を通してポップというか、表現がこれまでの作品に比べて、ストレートになっているように感じたんです。
MORRIE:そうね、色んな人の感想を聞くのも楽しいよね。今回はギターを結構弾いているんですけど、テクニカル的には簡単……というと語弊があるけども、自分が弾きながら歌うことを想定して作っている。ほら、Creature Creatureは弾いてくれる人たちがいるので、難しい部分もあるけど(笑)。ある意味ストレートになっているのかもしれないね。
――黒木さんのギターサウンドも、なんというか、ストレートなロックですよね。Z.O.Aのギタリスト、かつ、MORRIEさんと一緒にやるときに、こういったアプローチなのかと驚きました。
MORRIE:彼は元々ロックですよ。Z.O.Aはいわゆるロックの王道ではないかもしれないけど、印象的には違う。昔から、彼のルーツはロックの王道から来るものだと思っていました。
 MORRIE(撮影 大島康一)
MORRIE(撮影 大島康一)
――楽曲の構造もシンプルになっている印象があります。
MORRIE:意図的にそうしたわけではないけれど、さっきも言ったように、全曲で自分がギターを弾いているというのは大きい。
黒いギブソン・レスポール・カスタム、いわゆる「ブラック・ビューティー」を手に入れて。で、やっぱりマーシャルで、ガーンと音を出すわけじゃないですか。ロックの初心というか、少年時代の初心に帰るというか。そういう多分に衝動的な部分が出ていると思います。それでスタジオ入って、ギャンギャン音出して、リフを作ったりして出来た曲もありますし。
意図したわけでもなく、自然にそういうストレートかつ、シンプルになりましたね。いつもより音楽知性を使わなかったというか、歌に関しても、あんまり考えていなくて、こうしようああしようというのではなく、できるだけ自然に作為なく歌った感じ。聴き方によっては色々あるんでしょうけど、僕的には緻密に作ったわけではないんですよね。
――歌に関してもあまり考えてないとおっしゃいましたが、MORRIEさんのボーカル、特にファルセットのバリエーションが以前よりもさらに多彩になっているような変化を感じました。
MORRIE:大昔、DEAD ENDの初期から比べたら、同一人物とは思えないくらい変わっていると思うんだけど。当時はファルセットを出そうとしても、出なかったんですよ。何故かある時びっくりするくらい突然出るようになって。そもそも、あの頃は基本的に地声で歌わないと男じゃない、ロックじゃないという「地声主義」のような時代でしたし。
僕らの世代はハイトーンでヘヴィメタルをやっている人はヘッドボイスを使っていたけれど、基本的に地声でしたね。地声主義って喉を潰すんですよ。バックもうるさく、スタジオPA設備も貧弱なので声を張り上げざるを得ないし、3日連続ライブがあると最後はボロボロでしたからね、あの頃は。
そういうのも馬鹿らしいなと思って、『BLUE VICES』(1988年・シングル)で、初めてファルセットを使ったのかな。
 MORRIE・3月4日キネマ倶楽部公演(撮影 大島康一)
MORRIE・3月4日キネマ倶楽部公演(撮影 大島康一)