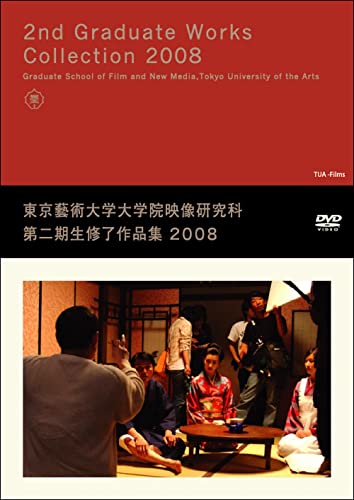オーディションで俳優を選ぶ基準とは?
濱口監督と言えば、ロカルノ、ナント、シンガポールほかの国際映画祭で主要な賞を総ナメにした5時間17分の大長編『ハッピーアワー』(15)でも演技経験のない4人のヒロインに対して実践し、『ドライブ・マイ・カー』の劇中にも登場する「イタリア式本読み」(感情を入れずに話す手法)で有名。
フランスの名匠ジャン・ルノワールが使っていたこのメソッドは本作でも取り入れられたが、感情を入れずに話すその手法を繰り返しながら、監督はひとりひとりの役者の中にあるものをどのように引き出していくのだろう?
「本読みすること以上に本質的なことは、役者に安心してもらうことです。もっと言えば、芝居の基準を自分の外に設けなくてもいいんだと思ってもらうことが大事ですね。
役者さんは普段は(監督や演出家に)ジャッジされる立場なので、どうしても演出家が芝居の基準を持っていて、その基準に向かって行かなければいけないと考えがちですけど、そうではない。
あなたがセリフを言えば、それが正解なんです。それで成立するんです。そう思ってもらうようにコミュニケーションを重ねているつもりです」
オーディションで役者を選ぶときも「“この人がセリフを言ってくれるんだったら大丈夫”という覚悟をするのは、自分がある程度好きになれる人じゃないと難しい」と前置きをした上で話を進める。

「さっき話したことと近いですけど、オーディションで役者さんが質問の正解を演出家が持っていると考えて、この場の正解は何だろう?って探るようなコミュニケーションをすると、『そうじゃない』と言いたくなる。
そんなことは考えずに、普通に1対1の関係として話してもらった方がありがたいし、その方が一緒に仕事ができるかもしれないという気持ちになるんです。ただ、勿論それは難しいことなので、できる限り雰囲気を和らげたいとは思っています」
芝居の場でもそれは同じで、「自分がセリフを言えばそれだけで成立するということを信じている役者さんたちが演技をし合うと、相手に対して驚く瞬間も起こるんです」という。
「“あっ、こんな風に言うのか?”“ここでこんな行動をとるのか?”っていう驚きが双方の役者さんの中に起きて、それがだんだん渦になっていったり、相互作用みたいなものが始まっていくような気がしています。
なので、役者さんには、自分がキャスティングされたことをとにかく信じてもらいたい。あなたがそのセリフを言えば、それがOKなんです。あなたはそういう風に選ばれたんです、ということを分かってもらうようにしていますね」
その言葉に嘘がないことは、「映画を観る立場としても、その場に巻き込まれちゃっている俳優さんが素敵だなと思います」という発言が実証する。
「僕は自分をコントロールするような芝居をする俳優には正直あまり魅力を感じなくて。それより、その現場に飛び込んで、そこで起きたことに対して素直にリアクションをするような人が好きです。
そういうときはだいたい現場全体がいいんだと思いますけど、そういうふうに映っている俳優さんは魅力的に感じられます」
監督が語る、『偶然と想像』演出のこだわり
 『偶然と想像』12月17日(金)より、Bunkamura ル・シネマほか全国ロードショー ©2021 NEOPA / fictive
『偶然と想像』12月17日(金)より、Bunkamura ル・シネマほか全国ロードショー ©2021 NEOPA / fictive
『偶然と想像』で行った、『ドライブ・マイ・カー』を視野に入れながらの実験や試み、演出上のテーマなどについても語ってもらった。
「第一話は言うまでもなく車のシーンです。夜の車のシーンをどう撮るか? 車中で会話をするシーンはどんな感じになるのか? 前に撮ったこともあるんですけど、それを改めて復習しておきたかった。
で、第二話ではいままでやったことのなかった性的な話をやっておこうと思って。肉体的な接触のある場面をどう撮るのか? そのときに、どういうコミュニケーションをするのか? ということを確認しておきたかったんです。
第三話に関しては、漠然と“演じること”について考えてみるといった意図でした」
そういう実験や試みができたのも短編集だったからだ。
「今回の三つの話はどれも他愛のない日常からインスピレーションを得た小っちゃい話です。こんな小っちゃい話は長編映画ではできない(笑)。
長編はもっと話に“うねり”がないといけないし、リアリティを緻密に構築していかなければいけないことが多いけれど、短編だったら、登場人物の関係性がピークに達したときにパッと終わって鮮烈な印象を残すことができる。
現実からちょっと浮いたような話をやりやすかったりもしますよね」
そんな短編だからできた驚きのショットが、第一話のラストシーンに早くも登場する。
 『偶然と想像』12月17日(金)より、Bunkamura ル・シネマほか全国ロードショー ©2021 NEOPA / fictive
『偶然と想像』12月17日(金)より、Bunkamura ル・シネマほか全国ロードショー ©2021 NEOPA / fictive
「第一話はいちばん分かりやすい三角関係の話で、第二話は人間のイヤなところを描いたダークな話。
それに対して第三話は明るい話に振って、気持ちよく終われる構成です。ただ、第一話はいちばん曖昧に終わってもいい構成上の位置だったので、試してみたかった終わり方にチャレンジしてみました。
あれを長編でやるのは、やっぱり怖いわけです。ああいう終わり方をして、観客がモヤッとした気持ちで映画館を出ていかれてしまうのは。
でも今回は、あの後に第二話、第三話が続いて、観客に感情的な解決を経た上で映画館を出てもらえる流れがあったので、あれをやってみたんです」
全三話を通じて、観客が段々と“偶然”に慣れていくようなつくりにしている

それこそ、本作の主題のひとつでもある“偶然”を作劇上で自然に表現するのは至難の技だが、濱口監督は「そこに対するいちばんの工夫はタイトルにつけるっていうことですね」とさらりと言ってのける。
「“偶然”は現実に生きていれば誰でも出会うものですけど、物語の中でやると語り手の思惑が見えて、ご都合主義に思われてしまいます。
しかも、人と人の因果関係を展開していくのがストーリーテリングだとすると、その因果関係から外れたところからやってくる“偶然”は異物でしかない。
でも、タイトルに入れてしまえば、観客も“これは偶然についての話なんだ”という気持ちで接してくれる。これは今回やってみていちばん感じていることですけど、“偶然”をまず許容してくれた観客は“いやいや、そんな話ないでしょ!”という気持ちにはならずに“それで?”というスタンスになってくれた。
一度受け入れてくれさえすれば、映画と現実がより近づいてくれるし、物語世界がより広く、深くなっていくような感触を持つような気がしています」
と言うことは、第一話で観客を上手く“偶然”の世界に引き込めれば、第二話、第三話も行ける! と踏んでいたのだろうか?
「全三話を通じて、観客が段々と“偶然”に慣れていくようなつくりにしているつもりです。第一話では芽衣子だけはどこかのタイミングで気づいている“偶然”は観客が気づかないうちに起きるので、おそらくツッコミは避けられる。
最後に起こるめちゃくちゃあからさまな“偶然”は、さっきのような理由で、観客も“こういう世界なんだ”って受け入れてくれるような気がします。」
「でも、第二話の“偶然”は現実の生活ではなかなか起こらない」。そう断った上で、濱口監督は「その“偶然”のあり得なさのレベルが二話、三話になるに従って上がっていっています」と告白する。
「それこそ、第三話が描くような偶然は現実的にはまず起こらないだろうけれど、この流れだったらあるかもしれないとむしろ観客には思ってもらえるんではないかと。
そうやって、“偶然”というものを段階的に受け入れていってもらうようにしました」
前述の俳優に芝居を任せる側面はあるものの、さまざまなメソッドを使ってクリエイトする濱口監督は撮影現場をすべて完璧に自分でコントロールしながら映画を作っている印象が個人的にはある。
“偶然”は映画にとって本質
そんな彼が、自らの映画演出や映画表現における“偶然”性をどれぐらい重要視しているのか? 気になって聞いてみると「“偶然”は映画にとって本質です」という思いがけない答えが瞬時に返ってきた。
「映画撮影のひとつの本質と言うか、“偶然”をとらえない限り、カメラはいま現在をとらえているという感覚を観客に伝えないような気がします。
別の言い方をするなら、過去の映像を観て、いま、まさに何かが起こっているんだというようなことを覚える感覚は、基本的に“偶然”がとらえられているときじゃないかと思っているんです」
「本読みを何度も何度もやるのも“偶然”を準備する作業です」と主張する。
「無感情で何度も何度もやってもらって、一語一句を口を突いて出てくるようにしてもらうので、僕がコントロールしている側面は間違いなくあります。
けれど、相手役の反応を見ながら、その限定されたセリフを見聞きすると、その人自身の身体の反応みたいなものがある種の“偶然”=アクシデントとして出てくるようなことがある気がしていて。それがいま、僕が狙っているものと言うか、撮ろうとしているものです」
“偶然”をとらえたときの映像の力強さは驚きに満ちたものになる
思えば、濱口監督の東京藝術大学大学院映像研究科の修了制作でもある初期の代表作『PASSION』(18)のラストシーンでは、カメラの前を大きなトラックが横切る“偶然”が衝撃的だった。
「あれを現場で最初に見たときは“役者が轢かれちゃうじゃないか!”って思ってNGテイクかなと思ったんですけど、あとで改めて見直したら、そのトラックはただフレームに入ってきただけではなく、ふたりの人物と同期していて、大きくUターンするところが彼らの心変わりの瞬間とも重なっていた。
そういう偶然の一致が何重にもあるあのシーンは、率直に言って、あの映画の中で最も力強いものになったと思います。演出家としてはある種の敗北感もありましたけど、そのときに、まさにこれこそが“演出”なのではないか! ということを啓示のように教えられました。
“偶然”をとらえたときの記録映像の力強さは、フィクションであっても……いや、フィクションだからこそ驚きに満ちたものになるという確信を得たので、あれ以降も“偶然”を自分の演出によってコンスタントにとらえ続ける方法を探し求めながら映画を撮っています」
 『偶然と想像』12月17日(金)より、Bunkamura ル・シネマほか全国ロードショー ©2021 NEOPA / fictive
『偶然と想像』12月17日(金)より、Bunkamura ル・シネマほか全国ロードショー ©2021 NEOPA / fictive
いずれにしても、世界的に高く評価された『ドライブ・マイ・カー』とそれと呼応するように誕生した『偶然と想像』で、濱口竜介監督の未来はさらに広がったのは間違いない。
「この2作は、自分の中では本読みを突き詰めていくという性格を持ったプロジェクトでもあって、それがひと段落したような感覚もあるんです。なので次作では、この2作でつかんだものを活かして、まったく趣の違う映画を撮れたらいいなと思っています」