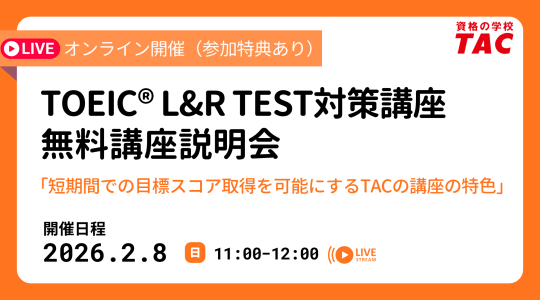――本番に入っても、公演ごとにすべて内容が違ったりして(笑)。
森山 その可能性はあります(笑)。
岩井 なくはないね(笑)。大人と子供の共犯関係。
――岩井さんや森山さんの解釈は、子供にも伝えたんですか?
岩井 城崎で子供たちに物語を作ってもらうワークショップをやって、未來くんがその中の『虹色の馬』という話を独自の解釈で表現したときに、書いた子は原作者として怒ってましたよ(笑)。
アフタートークのときにニコニコしながら「私が書いたのと全然違う!」って(笑)。そのやりとりもすごく面白かった。
――面白いですね。
岩井 もちろん、ストレートにやった作品なんて一個もないんですけど、ああいう表情で、「何してくれてるの?」みたいな感じで対等に絡んでくる。
もちろん、全編違うことになってるわけじゃなくて、大人たちが自分の書いた台本を面白くしてくれた部分もあるし、何やってくれてんだよ?っていう感情もあるだろうし、やったこと自体も残る。
その場では「私のホンが元になっているんだから」っていう自負もありありなわけで、けっこう対等なスタンスでいるのが面白かったですね。
子供 VS 話が壊れていれば壊れているほど、面白がる大人たち
――原作者ですからね。
岩井 そうそう。子供たちにとって、その経験がすごくいいと思いましたね。これを5、6年も続ければ、ひとりぐらい作家が出てくるんじゃないかという気がしたぐらい。
どっちかと言うと、話が壊れていれば壊れているほど面白がる兄ちゃんたちが相手だったりするから、彼らもかなり面白いと思います。
それこそ僕は、中一ぐらいのときに自分の自画像の顔を緑色に塗ったら、最初は面白がっていた先生に「いつ、岩井は顔を肌色にするんだ」って言われたことがあって、それがかなりトラウマになってるんですよ。で、そういうことを経験すると、ほかの選択場面が来ても自分に確信がない限り、“あっ、肌色にしよう”という思考になっちゃうと思うんですね。
でも、城崎ではその逆で、自分の書いた文章をよりえげつない大人たちがさらにブーストかけてもっとすごい緑色にしたわけで。
そういう経験をしていると、自分が「やりたい」と思った表現を信じなくちゃいけない局面でも戦うことができる。僕は勝手にそう信じているんですけどね。別に自分がそう感じたんだから、それでいい。
「普通に考えたらそうじゃないよ」って言われても、自分の感じたものを曲げる必要はないし、そこで戦うことの方が大事だと思います。
――今回は「大人も子供も楽しめるもの」を念頭に置かれていますが、そこは見せ方の面でも意識してますか。
岩井 「大人も子供も楽しめる」って一応言っておいて、こっちは気にしないというのがルールです(笑)。
僕はさっきも言ったように、最初は子供向けの作品をやろうとしていたんですね。子供の目線まで降りて行くものを。
でも、未來くんと話しているうちに、降りていかない方が面白そうだし、そっちの方が意味があると思ったんですよね。別に大人が観るようなものを観ても子供も面白がれる瞬間はあるし、さっきのアニメとアニメの間の成人映画を観ちゃうような体験でも何かしら感じるわけです。それが象徴的だったのは、前野くんが城崎でやった音楽のワークショップで。
前野くんはそこでビリー・ジョエルの「Honesty」やT・レックスのグラムロック、浪曲を子供たちに聴かせて、曲を聴いて閃いたイメージをホワイトボードに書かせたんです。
そしたら、「Honesty」のときに「別れ」とか「卒業」とかけっこうバシバシ出てきて。「英語」っていうのもあったけど(笑)、大人と感覚はまったく変わらないんですよね。
で、浪曲を聴かせたときも「日本の昔の~」って国までバシッって的を得てたり、雰囲気もつかんでいた。それを見ながら、ああ、そうなんだって思ったし、自分も同じだったなって思い出しましたね。
そういう感覚って、別に子供だからとか大人だからっていうものではないし、分け隔てなくやっていった方がこっちも面白い。観る方だって親も子供も感じる面白さは変わらないから、子供が観るからということは敢えて考えないようにしました。
今回のプロジェクトはそこがすごく大事なことだと思っているんです。
*
「なむはむだはむ」では、岩井と森山が、母親と子供が一緒に観劇できるような舞台と客席のフレーム作りも考えた。さらに、どの年齢の子でもお母さんの膝の上で観られるマチネ(昼の回)を平日と日曜にそれぞれ1回ずつ設定。
そのほかの回も子供料金を設け、各回とも最前列の自由列では、子供が多少騒いだりしても大丈夫なようなフォーマットになっている。
しかも、公演時間は子供たちの忍耐力を考えて約60分を予定している。
――子供たちが「ワーキャー」騒いだり、走り回ってもOKなんですか?
岩井 いや、怒りますよ。「何、してるんだ」って言いますよ。でも、城崎で1回、途中経過の発表をやれたのが感覚としてはすごく大きくて。
最前列で観ていた子供たちがリアクションを言葉にするし、城崎の場合は特にワークショップに来ていた子たちがいたから、その子たちが自分の書いた台本だってアピールしながら観ているようなところもあったんです。
それにそのほかのお客さんも子供が書いた台本というのは知っているから、この観客の中にこれを書いた子もいるかもれしないという意識もあって、その根源的な関係もすごく面白いと思いましたね。
――今回の公演でも観たことがないものが観られそうで、楽しみです。
森山 この話が子供たちから発信されたものであることは最初にエクスキューズしてあるので、ワケが分からないような感覚になったとしても、大人が作った抽象的な話のような退屈なものにはならないと思います。
大人は“これを子供が作ったの?”というニュアンスで絶対に観ちゃうと思うし、子供たちはすごく自然な反応を返すだろうから、僕らが真面目にやればやるほど、子供たちのためにやってますという感じにならなければならないほど、ヘンに笑っちゃったりヘンに身構えちゃういわゆる“オトナ”にフィードバックされていくような気がしていて。
子供を見ているような気分で観ている大人と、そんな自分を客観的に見つめ始める自分という構造が自然と生まれると思います。