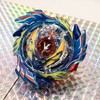2年前より“挑戦したい”感が増えました
――初演のとき、とくにお子さんたちに“ウケた”シーンはどこでしたか?
馬がおじいさんの皮を剥いでおじいさんになりすますシーンがあるんですが、そこは大人よりも直観的に楽しんでくれていましたね。
その上で、「痛い」ということがちゃんと「痛い」こととして届いた、とも感じました。
今回、「痛いことは痛い」とちゃんと伝えよう、と思っていて。皮を剥ぐほうも心が痛いし、剝がされる方も身体的に痛い、っていうところをちゃんと表現しておきたいなと思っていたんです。
扱っているのも「気づかい」というテーマですから、ただ面白いこととして届けるのでは、「気づかい」というもの自体がふわっとしてしまう、という思いがあって。気づかいがあるから痛みも感じる。それが子どもたちの感覚的なところで響いたんじゃないかなと思っています。
――お子さんに伝わったと感じた瞬間は、大人向けの作品のときとは違いますか?
めちゃめちゃ救われますね、こちらが。素直にうれしかったですね。
子どもはかつての自分なんですよね。無意識に境界をひいてしまいがちですけど、じつは今の自分と地続きであることを忘れちゃいけないなと思っています。初演から2年たって、僕ら自身も感じることがいろいろ変わってきていると思いますし。
――ノゾエさんご自身も今と2年前で、変わっていますか?
そうですね、まず、老いてますね(笑)。あとは、2年前より今のほうが“とげ”が出てきているような気もします。“挑戦したい”感が増えている気はしますね。
 「子どものころから、お話を考えるのが好きでした」と語るノゾエさん
「子どものころから、お話を考えるのが好きでした」と語るノゾエさん
――その“とがった部分”が再演の見どころですね。
そうですね。今回は再演ということで、一度作り上げた状態から始まるわけです。僕はそこで一度ゼロにすることが大事だと思っていますが、その一方で、熟成度は確実に変わるんだろうとは思います。
一度たどり着いたところをみんなでもう一回考え直し、感じなおして、作り直すっていうのが。その結果、“熟成肉”のような味が出ていればうれしいですね。
親も子も“気づかい”合えることが幸せ
――今作のセットは「ジェンガ」(木製などのパーツを交替で積み上げたり引き抜いたりしていくイギリス発祥のテーブルゲーム)をイメージしたものになっていますが、ノゾエさんはお子さんのときどんな遊びが好きだったんですか?
空想好きでしたね。よく自分で紙に何か書いたりしてゲームを作ってましたね。お話を考えるのも好きでした。小学校の学芸会でも、演劇をやるとなったら脚本を書いたり。
でも親は厳しかったですね。勉強、勉強でしたね。そういう制約や抑圧があったから、空想だったり表現するっていうことが楽しくなったのかもしれません。
大学に入った時点では、普通に「いい企業に入る」ということしか考えていなかったです。そういうものだと思い込んでましたね。
――何をきっかけに将来の方向が変わっていったんですか?
大学で演劇を始めてからですね(笑)。もう、全部が楽しくて。気がついたら単位も落とし始め、留年し、就職する気にもなれなくて。
まずいなぁと思っていた大学4年の頃に、松尾さんに出会い、プロに近い世界を知って、さらに演劇にハマっていったっていう感じですね。親は今でも「征爾は一体誰の血なんだ…。突然変異としか思えない」って言ってますね。嬉しそうに(笑)。
当時はなんて怖い親なんだろうって思ってましたけど、今になってみると抜けてたなって思うところもあって。たとえばお箸の持ち方とか。
そうか、ここは見逃されたんだなって(笑)。親もやっぱり手探りで“親”をやっていたんだなって思います。大人になってから急に「あの時ああいうこと言っちゃってたけど」って反省の言葉をかけられたりね。お互いに、“気づかい”あってたのかなって思いますね。
――親子関係って客観的になれない分、難しいですよね。
何が正しいか間違ってるかわからない中で、その都度ちゃんと悩んで悔いて喜んで、せいいっぱい向き合うっていうことが親子にとって大切なのかなと思いますね。
――ノゾエさんのお父様とお母様もそういう風に全力で向き合ったから、今のノゾエさんがあるんですね。
僕はちょっと偏った人間ですけど(笑)。なかなか完璧にはね…って悩み続けることがいいことなのかな、という気がします。
今でもずっと親は親で、僕との距離を考えているでしょうし、僕も親との距離を考えますし。そうやって、“気づかい”続けられることが幸せなことだなって思いますね。
 ルーシーは気づかいのループから抜け出すことができるのか? 撮影:阿部章仁
ルーシーは気づかいのループから抜け出すことができるのか? 撮影:阿部章仁
開館25周年/芸劇フェスティバル「気づかいルーシー」
東京芸術劇場 シアターイースト
公演日:2015年8月22日~31日