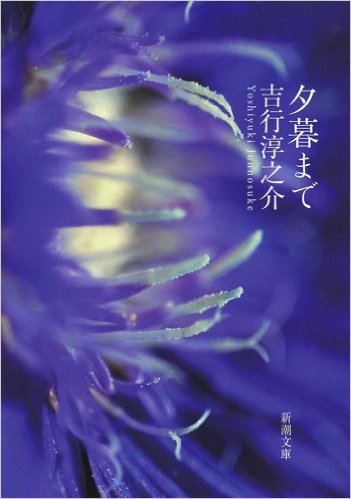どこまでもゆるやかだけれど、静かに壊れていく様子が恐ろしい。
最後にご紹介したい小説は、新興芸術派の作家、吉行エイスケと美容家あぐりの長男として生まれ、1954年『驟雨』で第31回芥川賞を受賞した吉行淳之介の作品です。
当時、淳之介と同世代の作家の庄野潤三、安岡章太郎、三浦朱門らとともに「第三の新人」と呼ばれるグループを形成した文豪ですが、吉行淳之介は「性」をテーマにした作品をたくさん描いています。
例えば、1978年に野間文芸賞を受賞した『夕暮まで』。
妻子持ちの中年男と、22歳の女性の奇妙な関係性が描かれています。
女性は、中年男との交際が始まった時には、処女であり、処女を守るために、最後までは絶対にさせません。代わりにオリーブオイルを股に滴らせるなど、その他諸々の本番以外の交渉は、少しも厭わずむしろ積極的に行います(!)この怪しい関係は、1年半近くも続きます。
設定だけ見れば、過激で、ドロドロの不倫小説かと思うのですが、実は全然そうではないのですね。7編の短編で構成された長編ですが、性描写も二人の関係も、感情も、あまりにあっけなく、いつも隙間風が吹き続けているような感じで描かれています。
それに、若い女性の方も、読み進めるにつれて、本当に処女であるかどうか、疑問も出てきます……。
ですが、女性が「真白なウエディングドレスが着れなくなるから」という理由で、中年男に最後までは決して許さなかったことや、中年男もその強く閉じられた脚を、自分の立場を考え、無理に開かせることはしなかったところなど……。
お互いの急所には踏み込まず、水面下で攻防戦を繰り広げていた様子に、男女の微妙な駆け引きと、虚しさを感じ、印象に残りました。
また、同じく作家「中田」と女たちとの危うい日常生活が鮮明に浮かび上る『暗室』という小説も、とても官能的なのですが、女性と深い結びつきを持つことを避ける男のお話です。
事故で亡くなった奥さんがいる「私(中田)」が、同性愛者のマキと、電話をかければすぐに会うことができる、多加子と夏枝という女性と何度も何度も関係を持つ様子が描かれているのですが、突如として「腹を上にして池の底に横たわる150匹のメダカ」の話や「知恵遅れのため、屋根裏部屋に隠されて暮らす兄弟などの逸話(※しかも、続きが気になる所でパタリと終わってしまう……)が挿入されているため、読んでいて、不思議な、モヤモヤする気持ちになる小説でした。
女たちは「私」の元を次々に、静かに去っていき、ゆるやか~に「私」が孤独を深めていく様子に、何度も違う女性と身体を重ねているのに、中々「暗室」から出てこられず、深い闇の中をさまよい続ける「私」が印象的でした。
今回ご紹介した「文豪」たちの作品は、驚くほどに、露骨な官能描写がでてきません。
女を鞭打つとか、奴隷のしるしをつけるとか、調教するとか、そんな設定は確かに物語の中心に存在しているはずなのに、もっと「性」の奥深くに存在している「生」、そして「死」に、否応なく向き合わされるお話でした。
なので、ドキドキしたりワクワクしたりなど、エッチな官能小説を読んでいる気分は中々味わえないかと思いますが、緻密で美しい情景描写や、人の心の奥底を見透かしているような文豪たちの目線に、ドキッとさせられてしまうことは間違いないかと思います。さすが文豪! と、美しい陶酔の世界にため息がでます。
良かったら、この夏ぜひ、文豪たちの官能文学に触れてみて下さいね。