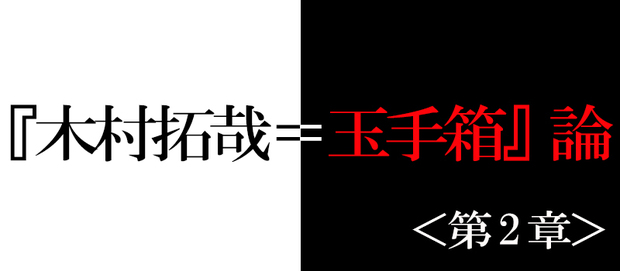
前章で「キムタク」は一種の呪文なのだと書いた。では、どのような呪文か。
まず、最初に確認しておかなければいけないのは、「キムタク」は木村拓哉のことではない、ということである。「キムタク」とは、木村拓哉のベルソナ(仮面)であって、木村拓哉そのものではない。しかも、木村拓哉本人が作り上げたペルソナではなく、わたしたち大衆が作り上げたペルソナだということを念頭に置く必要がある。
彼が生放送に出演したときの、“言い知れぬ緊張”の正体
芸能人と呼ばれるひとびとが自らペルソナを作り上げるのはごくごく当たり前のことであって、たとえば芸人は自身でパブリックな芸風を確立することができなければ、ほぼブレイクは難しい。いわゆる自己プロデュース能力は、とりわけお笑いの世界では必須のものだろう。
俳優にしろ、タレントにしろ、最近ではアスリートにしろ、彼ら彼女らが自ら必要に迫られて作り上げた芸風を、とりあえず、丸ごと大雑把に信じ込むことから、わたしたちの認知はスタートする。信じ込むとはどういうことか。バラエティ番組などで、彼ら彼女らが披露している芸風に、そのひとの「素」がさらされていると思い込むことだ。
もちろん、個々のコアなファンは、芸風と(妄想のなかの)本人との落差を楽しむのだろうが、一般的には「オバカ」「天然」「腹黒」などといった表層的かつ、お手軽な言葉でカテゴライズすることで「そのひとを手に入れる」。そしてこれら「オバカ」「天然」「腹黒」は芸能人自らが発信している「オフィシャルな」ペルソナだということを、現代の大衆はほぼ無意識に感じとっている。
木村拓哉がバラエティ番組、とりわけ生放送のそれに客演(前章に書いた通り、彼はバラエティ番組で「主演」することはない)したとき、言い知れぬ緊張が走るのは、木村拓哉本人から、彼発信の芸風がほとんど感じられないからではないだろうか。
誰もが木村拓哉に対して「わからない」と感じている
そもそも、バラエティ番組の常連ではない彼は、わたしたちが認識しやすい「素」を積み重ねる機会がない。もちろん、話し方や語り口の特徴はある。しかし、それらは生命体としての癖のようなものでしかなく、テレビ画面にほどよくおさまる「カテゴライズされたキャラクター」(それこそが、芸能人が自身で作り上げるペルソナであろう)ではない。
これが、映画中心、舞台中心で活動している俳優であれば、何ら珍しいことではない。「テレビに不慣れなひと」としてレッテル貼りされて、許容される(これは、社会生活でも同様で、わたしたちは誰かに対してレッテルを貼ることで許容するし、また、自己プロデュース能力が高いひとが発信する芸風を呑み込むことでその誰かを認知する)。
だが、日本人で知らない者がほぼいないであろう木村拓哉の、素性が不明であるとしたら? これは困ったことになる。彼は必ずしも「飛び道具」的に、なにかをやらかすわけではないにもかかわらず、芸風がキャッチできない「危険な」何者かとして、そこに居る。
木村拓哉が、画面から浮いているようにも思えるのは、彼のオーラの成せる技というよりは、わたしたちの誰もが、木村拓哉に対して「わからない」と感じているからではないのか。

























