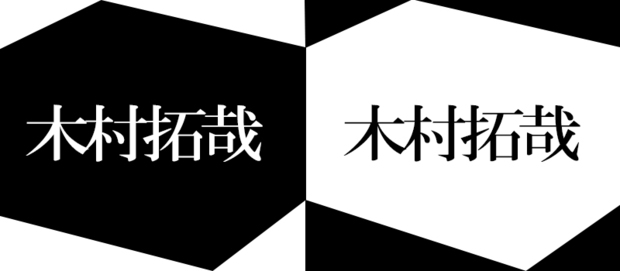
「わたしだけが、あのひとのことを、理解している」という幻
「わたしだけが、あのひとのことを、理解している」。
ファンが陥りがちな心理である。木村拓哉にかぎらず、あらゆる分野の、あらゆるジャンルのひとに、そのようなファンはついている。
現実生活に置き換えてみれば、それがただの勘違いであることはたちどころにわかるはずだ。たとえば、リアルな恋愛にせよ、どちらか一方にとってのヴァーチュアルな恋愛にせよ、対象が異性であれ同性であれ、「わたしだけが、あのひとのことを、理解している」という思い込みは、自身の感情を高める上で効果的に作用するし、その「沼」につかっているうちは、なにごとかを信じている気分になることができる。
だが、あるとき、気づいてしまう。自らが「沼」から這い出ることもあれば、いつの間にか、その「沼」が干上がっていることもあるが(いずれにせよ、「沼」など、どこにもないし、すべては妄想にすぎないのだが)、「わたしは、あのひとのことを、何もわかってはいなかった」と。
そう。「わたし」は、「あのひとのこと」を、「自分の思いたいように思っていた」だけにすぎない、ということを知る。
「わたしだけが、あのひとのことを、理解している」。大それた思い違いの愚かさに直面したとき、ひとは失う。恋を失い、ファンという「安全領域」を失う。
かく言うわたしもそうであった。どうして、ひとは、木村拓哉の演技そのものを見つめようとはしないのか。どうして、これだけ多くのひとに愛されながら、だれもまともに、彼の芝居を論じようとはしないのか。「木村拓哉はなにをやってもカッコいい」――聞こえてくるのは、そんな大合唱ばかり。
「わたしだけが、木村拓哉の演技を、見つめている」。そう錯覚した時期も確かにあった。だが、それはすべて幻だったことを、映画『HERO』の撮影現場に12回足を運んだ末に、はっきり知覚した。























